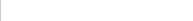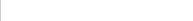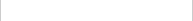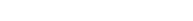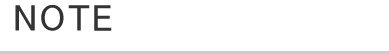【知財高裁判決紹介】音楽マンション事件(商標法3条1項6号該当性)
2018-01-26
知財高裁平成29年5月17日判決(平成28年(行ケ)10191号)は,概ね次のとおりの判断し,特許庁が無効2015-890094号事件について平成28年7月4日にした審決(商標法3条1項6号に該当せず)に誤りはないとしました。
1 裁判所の判断
「本件商標は,『音楽マンション』という文字から構成されているところ,音楽という文字とマンションという文字をそれぞれ分離してみれば,前者が『音による芸術』を意味し,後者が『中高層の集合住宅』を意味するところ,両者を一体としてみた場合には,その文字に即応して,音楽に何らかの関連を有する集合住宅という程度の極めて抽象的な観念が生じるものの,これには,音楽が聴取できる集合住宅,音楽が演奏できる集合住宅,音楽家や音楽愛好家たちが居住する集合住宅などの様々な意味合いが含まれるから,特定の観念を生じさせるものではない。」「『音楽マンション』という文字は,原告が使用する『ミュージション』と同様に,需要者はこれを造語として理解するというのが自然であり,本件商標の指定役務において,特定の役務を示すものとは認められない。」「『音楽マンション』という文字は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえない。」「『音楽マンション』という文字が,個別具体的なマンションの意味を超えて,マンションの一定の質,特徴等を表すものとして一般に使用されていたものとは認められない。」「『音楽マンション』という文字は,これが使用されている実情等を踏まえても,特定の観念を生じさせるものとは認められず,本件商標の指定役務において,特定の役務を示すものとはいえないから,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえない。」「したがって,本件商標は,商標法3条1項6号に該当するものとは認められない。」
2 ワンポイント解説
ある商標について、自他商品又は自他役務識別力を否定するためには、基本的には直接的かつ具体的に特定の質、特徴等を表すものとして認識され得ることが前提となります。これに対し、ある商標から漠然と何等かの質、特徴等を暗示させる程度、あるいは間接的に表示するにとどまるものは、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を発揮し得ます。このような判断枠組みは、特許庁審査・審判実務、裁判実務で概ね採用されてきたものです。
商標「音楽マンション」(指定役務:第36類「建物の管理,建物の貸与,建物の売買,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建設工事,建設工事に関する助言」)についての特許庁審判部及び裁判所の判断は、いわゆる暗示的商標又は間接的表示に関し、過去の審査・審判・裁判実務から乖離する判断ではないといえますが、本判決において注目すべきは、判断の理由中に、「音楽マンション」について過去に出願をしていた原告(無効審判の審判請求人)のこれまでの特許庁手続上の主張等について言及されている点です。
例えば、「音楽マンション」の商標法3条1項6号該当性の判断をするにあたり、裁判所は、「かえって,原告自身も,・・・平成14年8月30日,『音楽マンション』につき商標登録出願をしたものの,平成15年5月6日付けで拒絶理由通知を受けたことから(甲7の1),同年6月23日,意見書を提出しているところ,同意見書において,『音楽』と『マンション』を並べても『音楽の演奏が可能なマンション』という意味合いが生ずることはなく,上記朝日新聞夕刊(大阪)に掲載された『女子学生に音楽マンション』という見出しについても,『音楽』には防音,演奏という意味を含まないため,上記見出しはどのようなマンションであるかを理解することができず,『音楽マンション』という文字がマンションの品質に係る役務であると認識されることはない旨主張していたことが認められる(甲7の4)。」ことを指摘しています。
また、原告が「本件商標と同一の文字からなり同一の指定商品又は指定役務に属する『音楽マンション』につき,特許庁は過去において拒絶査定をしたにもかかわらず,本件商標を登録査定したのは,平等原則,禁反言の原則,信義則にそれぞれ違反する」と主張したことに対し、裁判所は、「『音楽マンション』という文字は,本件商標の指定役務において,特定の役務を示すものとはいえず,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえないから,本件商標は,商標法3条1項6号に該当するものとは認められない。」「そうすると,上記拒絶査定は,どのような資料に基づいて判断されたかは必ずしも明確でないものの,商標法3条1項6号該当性についての判断に誤りがあるものといわざるを得ないから,これに対する不服審判請求に係る審決等において取り消されるべきものと解される。」「それにもかかわらず,原告は,不服審判請求をするなどして正しい判断を求めなかったのであるから,原告の主張は,失当であるというほかない。」と指摘しています。
これら指摘は、特許庁による拒絶理由通知書、拒絶査定書、拒絶審決について十分に検討・精査し、それらへの対応方法についても的確にすべきことを示唆するものです。
客観的かつ公平な判断が如何なるものであるかは、実務において常に考えることは必要です。特に識別力の有無や商標の類否についての判断は、判断者の個人差がある中で、個別具体的事件の中で客観性ある公平な解決を求める姿勢が重要といえます。
特許庁の審査において、拒絶理由通知書を受けた場合でも、直ちに諦めるのはでなく、1人の審査官による当該判断が真に妥当なものであるか検証が必要であり、その後の特許庁審判部や知財高裁ではなお同じ判断がなされ得るのか、異なる判断が期待される事案か、など早い段階で適切に把握することが大切です。