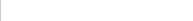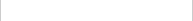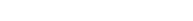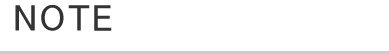著作権の改正(新しい裁定制度等の導入)
2023-05-29
改正著作権法が令和5年5月26日に公布されました。
改正著作権法の内容は以下の通りです。
1:著作権法で新たな裁定制度(「未管理公表著作物等」)(67条の3)ができた経緯
⑴ 既存法の問題点
著作権者等が不明であったり、著作権者等の許諾可否に関する意思が確認できなかったりする著作物多くあり、こ
れらを利用する場合にも、著作権者の承諾を得ることが必要です。しかし、著作権者が不明の場合は承諾を得ること
ができません。
この場合、既存法では文化庁長官に対して裁定(著67条等)がありますが、裁定を求める要件が厳しく、処分まで
一定期間を要していました。
なお、裁定処分までの間でも、裁定申請と同一の方法により著作物の利用ができる旨の規定があります(著67条の
2)が、上記のような場合、当該裁定を認めることができるか不明確です。
⑵ 新たな裁定制度の導入
そこで、上記のような場合に対応すべく、著作物を利用できるような新たな裁定制度(新67条の3(新設))を設
けることとされました。新たな裁定の制度は、要件が緩和されています。(①裁定を求める際の理由が著作権者不明
の場合等と限定されていない、②補償金を供託する必要がありますが、「指定補償金管理機関」が補償金管理業務を
行っている場合には、指定補償金管理機関に支払えば足り、供託の手続をとる必要はありません(第104条の21第2項
)。なお ②の要件は著作権者不明等の裁定(67条等)でも採用されます)。
なお、本裁定は従前にある裁定制度とは異なり、最大裁定から3年間利用を認めるというものにすぎません(新67
条の3第5項)。
そこで、長期間の利用を欲する場合には、従来の裁定制度(67条等)を求めるか、再度、本裁定(新67条の3)を
求める必要があります。
◆ 本事項のみは、各機関などとの調整が必要であることから、公布から3年以内に施行がされます。
2:立法・行政の目的のための内部資料としての著作物の公衆送信等
⑴ 現行法の問題点
立法・行政目的のための内部資料として著作物を利用する場合には、複製ができるとされ、公衆送信は規定されてい
ません。これは、現行法では立法・行政における第三者の著作物等の利用について、紙媒体によるものが念頭に置かれ
ているからです。
⑵ 公衆送信権の規定の導入
しかし、社会の変動に伴い、紙媒体等に複製せず、公衆送信をする場合が多くみられます。
このため、立法・行政目的で利用する場合には、公衆送信ができる旨を規定することにしました(新42条)。
◆ この改正事項は、令和6月1月1日に施行されます。
3:損害賠償額の算定基準の変更
⑴ 現行法の問題点
産業財産権法では、令和元年の特許法102条1項・4項等の改正により、損害賠償額の算定基準が変わり、侵害に対し
て妥当な損害額が認定できるようになっています。
これに対し、著作権法では、産業財産権法のような改正がなされていませんでした。
⑵ 妥当な額が認定できるような改正
しかし、近年の海賊版サイト等による著作権侵害の被害の増加に対し、さらなる実効的な対策の必要性が高まっていま
す。
そこで、著作権も産業財産権と同様の改正がなされます。
◆ この規定は、令和6年1月1日に施行がなされます。
参考:文部科学省ホームページ
著作権法の一部を改正する法律案(概要) (mext.go.jp)