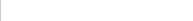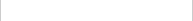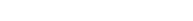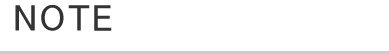意匠法改正の動向について(第1回)
2025-07-03
【意匠法改正の動向について(第1回)】
現実空間の物品等のデザインを模した仮想オブジェクト等を第三者が無断で販売等するケースが増加し、意匠法の改正が令和6年12月6日以降の産業構造審議会知的財産分科会で議論されています。産業構造審議会での議論を元に、意匠法改正の動向について今後説明を行っていきます。
第1回目は意匠法を含めた上での現行諸法での取り扱い、意匠法改正の方向性について説明していきます。
1:我国での対応(現行制度)
仮想空間のデザインについての我が国での法制としては、意匠法、不正競争防止法、著作権法が想起されますが、諸法共に以下の点で問題があります。
⑴ 意匠法
現行の意匠法では、保護対象たる意匠は、①物品の意匠、②建築物の意匠、③画像意匠です。このうち画像意匠は産業の発達との観点で、操作画像又は表示画像のみが登録され、現実空間の物品等のデザインを模した仮想オブジェクト等を第三者が無断で販売等するケースにおいては、①登録意匠に係る物品等とその形状等を模した仮想オブジェクトは、用途・機能が異なる場合が多く、その場合、意匠の類似が認められず意匠権の侵害とはなりません。また、②物品等の意匠の実施は有体物に対する行為を前提としているため、無体物である仮想オブジェクトの販売等は実施に該当しないと考えられ、意匠権侵害の責を問うことは困難です。
⑵ 不正競争防止法
令和5年改正された不正競争防止法2条1項3号ではそのような模倣(仮想オブジェクト)に対し、形態模倣として差止や損害賠償等(不正競争防止法3条、4条)を求めることができる。但し、不正競争防止法でその模倣行為を防止できるのは、国内販売から3年間に限定され、その形態に依拠して実質的同一性のあるものに限られます(不正競争防止法2条5項)。そのため、古い商品形態の模倣や類似範囲の形態模倣には対応が不十分です。
⑶ 著作権法
著作権法では、著作物が侵害された場合に差止等を求めることができますが、物品の形状等に係る仮想オブジェクトは、著作物性が否定され得る可能性があり、著作権法による保護では不十分です。
2:意匠法改正の方向性
⑴ 意匠で保護することの優位性
上記何れの法制からも、仮想オブジェクトに対する保護が不十分であり、依拠の有無に関わらず侵害の責を長期間(出願から25年間)保護すると共に、公報による公示を通じて抑止的効果もある、意匠法を改正することが必要ではないかという方向性が示されました。なお、改正に際しては、著作権と交錯する部分があることから、表現の自由との関係で著作権の制限規定(著作権法30条~50条(第5款))、クリアランス調査の負担が増大することのないような制度とすべきと提言されました。
⑵ 意匠法改正の方向性の模索
意匠法改正に際しては3つの類型が模索されました。
① 現行の類型(物品・建築物・画像の一部)以外に登録可能類型を拡大する方向性
この類型を認めた場合には、仮想空間でのオブジェクトが意匠登録されることになります。しかし、物品・建築物・画像といった既存の登録可能類型がある中でこれらとは異なる新たな登録可能類型を追加するにあたっては、法制化に向けて検討すべき事項が非常に多くなってしまいます。
② 物品及び建築物の意匠権について実施の範囲を仮想空間上に延長させる方向性
この場合には、クリアランス調査の負担が大きく、これまでの意匠の類否の考え方と整合しない、物品等の意匠の権利化やその権利の在り方に影響を及ぼす等の問題があります。
③ 現行の登録可能類型である画像の意匠において、操作画像及び表示画像に加え、物品等の形状等を表した画像を保護対象とする方向性
現行意匠法上、操作画像・表示画像に該当しない画像は保護の対象となりませが、当該改正案は、操作画像・表示画像に該当しない画像であっても、物品等の形状等を表した画像であれば、画像の意匠として保護の対象とします。
当該新たなタイプの画像意匠が登録になった場合には、同一又は類似の画像の意匠に及ぶこととなります。なお当該意匠権の効力は、物品等の意匠には及ばないとされます。*
*:現実空間に対して効力を及ぼすべきか否かについて
なお、補充ヒアリングにおいて、そのようなデザインが大量に意匠登録されることで、現実空間における創作活動にも萎縮効果をもたらす可能性があるので反対という意見、現実空間と仮想空間を交錯する権利行使を認めることは未知のリスクがあり、懸念があるとの意見が多数あり、現実空間での意匠には効力が及ばないものとされました。
現在の審議会での議論では、上記③の類型で(画像意匠の一部として保護)意匠を保護することで議論がなされています。
今後は、引例となる意匠との類否判断の要件、AIを利用した形態が、引例となり得るか等が検討されます。
【参考】
産業構造審議会知的財産分科会第 16回意匠制度小委員会令和6年12月6日
産業構造審議会知的財産分科会第17回意匠制度小委員会令和7年2月10日
産業構造審議会知的財産分科会 第18回意匠制度小委員会令和7年4月3日
添付資料・議事録