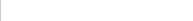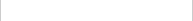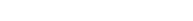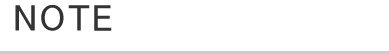意匠法改正の動向について(第2回)
2025-07-04
【意匠法改正の動向について(第2回)】
1 保護対象たる画像
現在の審議会の方針では、仮想物品等の形状は、「仮想物品等の形状等を表した画像」(画像意匠の中に新たな対象を取り組むという考え方)とすることで、実質的には、仮想物品等の形状等の保護を図ると考えられています。その特定は、仮想物品等の形状等を保護する方法として、仮想物品等の形状等を直接の保護対象とする方法もあり得ますが、一の立体形状等を有する仮想物品は、視点の変更とともに異なる形状をした画像が現れるものと考えられることから、任意の視点から見た場合に現れる無数の画像を一の意匠として保護することで、実質的には、仮想物品等の形状等を保護することとする予定です。
2 仮想物品などの形状の類否
意匠の類否は画像意匠を含め、対比する両意匠の形状等が同一又は類似であることに加え、対比する両意匠の用途及び機能が同一又は類似であることを前提としています。仮想物品等は現実空間で用いられる物品等と異なり、形状等と用途及び機能の関連性が希薄であり、何らかの機能の追加や削除をすること、機能に可変性があること、仮想空間においては物理法則の制約が及ばないために、現実空間にはない物品等の機能を持たせることができるといった実態があることから、仮想物品等の用途及び機能については類否判断を行わないという(形状等のみを基に類否判断を行うこと)ことも考えられます。但し、仮想デザインに係る意匠は画像意匠の類型として保護を認めるものであること、意匠権の効力は絶対的独占権であり強いことからも、仮想物品等の用途及び機能を超えた部分にまで調査負担等を課すのは酷であると考えらます。そのため、仮想意匠の類否判断は従来の意匠と同様、両仮想物品等の用途及び機能の同一又は類似を仮想物品の需要者を基準に行うこととして判断すべきであるとされています。なお、今後は更に類否判断の詳細や仮想物品等の実施行為とは何か、また誰の実施行為に該当するにかなどの点が議論される予定です。
3 AIを利用した創作
AIを利用した創作されたものは意匠に該当するのか(その関与の程度)、またAIを利用したものは短期間で大量に創作することが可能となることから、これを公知意匠や公知形態として3条1項(新規性)、創作非容易性(3条2項)の引例とすべきなのか?
またすべきとした場合、従来の意匠や形態とは異なる取り扱いをすべきか、新規性性喪失の例外(4条)の適用はどうあるべきかにつき、現行意匠法の各規定の趣旨やその解釈、デザイン創作に関わるステークホルダーが抱える懸念や課題、諸外国の法制度や議論の状況等をより具体的に調査分析等を引き続き行うこととされています。
【参考】産業構造審議会知的財産分科会 第19回意匠制度小委員会(配布資料・議事録)