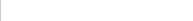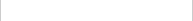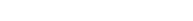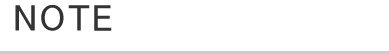商標法審議動向:第12回商標制度小委員会議事録の公開
2025-07-19
産業構造審議会知的財産分科会 第12回商標制度小委員会議事録が公開されました。
以下、前回のノート記載以外で特に議論がなされた事項を記載します。
仮想空間における商標の保護
【仮想商品と現実商品との間の類否】
1:登録の可否(特許庁判断)
現実の商品に係る他人の同一又は類似の登録商標が存在する場合、仮想商品と現実の商品は原則非類似と推定される。
なお、周知・著名の場合には商標法4条1項15号などに該当し登録は出来ない。
2:権利行使(裁判所)
他人が現実の商品に係る登録商標と同一又は類似の商標を仮想商品について使用している場合、仮想商品と現実の商品が類似と認められなければ、現実の商品に係る商標権に基づく権利行使は、原則としてできない。なお、この場合でも不正競争防止法2条1項1号、2号に該当する場合がある。
【仮想商品相互の類否】
1:登録の可否(特許庁判断)
仮想商品に係る他人の同一又は類似の登録商標が存在する場合、仮想商品同士は原則類似と推定されるため、仮想商品に係る商標は原則として登録不可。
なおこの見解に対しては、仮想商品相互が類似する場合には、一部の仮想商品について権利を取ったら、他人の商標登録を阻止できるのであれば、実質的に仮想商品全般について権利を取れることになる。 仮想商品同士が類似とすると、一部の仮想商品について商標登録をすれば仮想空間の中ではすごく広い範囲を押さえられることになる等の禁止権の範囲が拡大されることによる弊害があるとの反対見解もある。
2:権利行使(裁判所)
他人が仮想商品に係る登録商標と同一又は類似の商標を仮想商品について使用している場合、仮想商品同士が類似と認められれば、仮想商品に係る商標権に基づく権利行使は、原則として可能。今後引き続きは仮想商品空間のビジネス実体、司法判断の動向などを見ていく。
なお、今回あまり争点とはならない、仮想空間での役務提供と、従来の役務提供との類否について以下のように特許庁の方から説明がなされた。
【仮想役務関係】
役務の場合は、類否を考える際には2つのパターンがあるとし、類似する場合とそうではないとされる場合に分かれるとして説明がなされた。
1 仮想空間において提供される役務と現実の役務とで目的や提供に係る内容が一致する場合には相互に類似する。
ex:仮想空間におけるコンサートの企画・運営と現実世界におけるコンサートの企画・運営という役務。
2 仮想空間において提供される役務と現実の役務とで目的や提供に係る内容が異なるような場合は非類似。
ex:仮想空間において飲食物を提供する役務と飲食物の提供という通常の役務。目的、そして提供に係る内容が異なっているので、現時点では非類似と考える。
ただ、これらのことを踏まえて、各国での状況を整理しながら今後慎重に検討する。
生成AI技術の発展を踏まえた商標制度上の整理
商標は特許や意匠のような創作物ではない。そのため、商標法で考え得ることは以下のように整理できる。
1:人の登録商標を学習させる行為が問題になるか。
登録商標をAIに学習させる行為は商標法上の使用行為ではないため、商標権の効力は及ばず商標権侵害とはならない。
2:AIが生成したものに他人の登録商標が含まれている場合に、それを商品に付して販売する行為等が問題となるか。
通常の商標権侵害と同様、商標の使用行為になり商標権侵害となる。
3:出力されたAI生成物を商標出願した場合に登録は認められるのか
商標は創作物ではないことから、特段通常の商標出願と変らない。