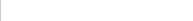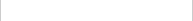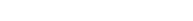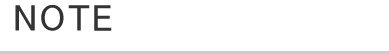仮想空間における意匠法での保護と問題点(産業構造審議会:意匠制度小委員会)
2025-10-30
2025年6月30日開催の第20回意匠制度小委員会では、「仮想空間上の物品画像」と「生成AIによる意匠創作」に関する制度的対応が具体的に議論され、意匠法の抜本的見直しに向けた方向性が明確化されました。
今後の進展がどうなるか、新たな審議会も開催での議論展開が待たれるところです。
【背景】
1:デジタル空間の拡大
メタバース、AR/VR、ゲーム空間など、仮想空間で使用される「物品画像」が急増しました。これに対し現在の意匠法では、有体物たる物品や建築物、画像についても機器等の表示画像また操作用画像に保護が限定されており、仮想空間上の立体物や画像は保護の対象外となるケースが多いことが問題となっています。
これに対し現行の不正競争防止法で対応することも可能ですが、以下の問題がありその保護が充分とはいえません。
⑴ 保護期間が国内販売の日から3年間と限定されていること。
→ 意匠のように出願から25年という長期間の保護はされない。
⑵ 登録制度がない。そのため侵害となるか否かの予見が立たない。
⑶ 不正競争防止法2条1項3号の模倣の立証が困難である。等が挙げられています。
2:生成AI技術の急速な進展
画像生成AIを利用することで、誰でも意匠的な画像を大量に創作できる時代になりました。そのため、以下の点が問題としてなり得ます。
【問題点・議論課題】
1:意匠の定義をどうするか
【問題の所在】
①意匠の定義自体に「創作」との文言がないことから、「意匠」(第2条第1項)は、定義上、物品等の美的外観に尽きるものであり、創作過程における人の関与を必ずしも前提としていないとの考え方があります。
②他方、現行意匠法は昭和34年に制定されたものであり、その当時、デザインの創作の担い手は人であった。そのため、意匠法は、近年の生成AI技術の急激な発達や、生成AIが従来人の担ってきた創作過程に関与してデザインを作成することを想定して制定されたものではないとの考え方もあります。
また、意匠法は、意匠の創作の奨励(第1条)を目的とする創作法であることも併せ考えれば、「意匠」(第2条第1項)は、創作過程における人の関与を当然に前提としているとの考え方もあり得るとの考え方があります。
ただ、上記いずれかの見解でも、人がAIを利用して創作した場合には意匠になることは明らかであり、少なくとも人が生成AIを利用して作成したデザイは意匠に該当するとして議論を進めてはどうかとされています。
引き続き、それ以外の画像(人が創作に実質的に関与していないものAI自律デザインを含む)が、「意匠」(第2条第1項)に該当し得るかについても、検討して行くこととされています。
2:AIが生成した意匠に対して、誰が創作者となるか。
AIを利用した画像の作成に関しては、以下の者の関与が想定されます。
【創作者として想定され得る者】
① AIの開発者、②追加学習によりAIのファインチューニングを行った者、③ AIに指示や入力をした者、④ AIが作成したデザインを評価・選択した者、⑤ AIが作成したデザインを調整・仕上げを行った者等どこまでが創作者になることができるかの議論がある
3:新規性や創作非容易性の引例として従来と同じような対応でいいか
→ 生成Aを利用したデザインが意匠に該当するとした場合、その数が膨大になることから、どのように扱うべきなのか
→ 仮に生成画像が引例となる場合、その基準はどうあるべきか。
→ また作成された画像が既存衣装の方か独自創作の判断が困難で出願が多く拒絶される可能性がある。
4:新規性喪失の例外適用をどうするか
生成AIの技術発達により、テキスト(プロンプト)や既存の画像を入力するだけで、短時間で大量の類似デザインが作成・公開されることが可能になりました。この結果、真の創作者(人間)が新しいデザインを創作し、そのデザインを出願する前に第三者がAIを利用して、類似のデザインを大量に生成・公開してしまう可能性があります。これにより、真の創作者のデザインが、その第三者の公開行為によって新規性を喪失し、意匠登録を受けられなくなるという問題(先回り大量生成問題)が懸念されています。
5:実行行為
① 保護対象の明確化
現行意匠法の操作画像や表示画像に加え、仮想物品等の形状等を表した画像を、新たな保護対象とする方向で検討が進められています。
② 実施行為の整理
仮想物品の実施行為を、現行意匠法と同様の概念で整理することとして議論されています。
・その対象は仮想物品等の形状等が、一の立体的形状を有し、任意の視点から見ることが可能なものであること
・(画像として表される)仮想物品等が、仮想物品等としての用途及び機能を備えていることを必要とする考え方が示されました。
③ 類否判断の基準
侵害の判断においては、仮想物品等の用途及び機能に基づき、類否判断を行うことが提案されました。なお仮想物品等は、必ずしも現実の物品等と同じような用途及び機能を実際に有しているとは限りません。そこで、たとえ類否判断の対象となる仮想物品等が現実の物品等と同じような用途及び機能を備えていなくとも、仮想空間で用いられる際の仮想物品等の形状等や、あるいはその使用方法などによって、特定の仮想物品等として認識させることも、当該仮想物品等の用途及び機能として認定することができる場合、この点につきましても考慮した上で、仮想物品等の用途及び機能の類否判断を行う。とされています。
【参考】
産業構造審議会知的財産分科会 第20回意匠制度小委員会速記録
意匠制度に関する検討課題について 産業構造審議会知的財産分科会 第20回意匠制度小委員会 令和7年6月30日