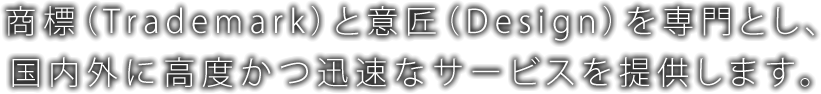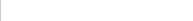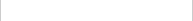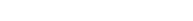2024-04-22
海外:商標
2024-04-22
海外:商標
2024-04-16
海外:商標法
2024-04-15
海外:お知らせ
2024-04-15
海外:商標
2024-04-07
2024-03-24
2024-02-28
2024-01-09
2023-12-25